実話を元に制作された『関心領域』が、
2024年5月23日に日本で公開されました。
「意味が分からない」
という声も多かった映画ですが、中でも、謎の少女とりんごのシーンが意味不明に感じられた人は、多かったようです。
謎の少女は、一体何をしていたの?
なぜそのシーンだけが、暗かったの?
そこで本記事では、謎の少女の正体や、りんごのシーンの意味について、どこよりも詳しくまとめてみました。
謎の少女が奏でた曲を書いた人物についても、併せて解説していきますので、お楽しみに。
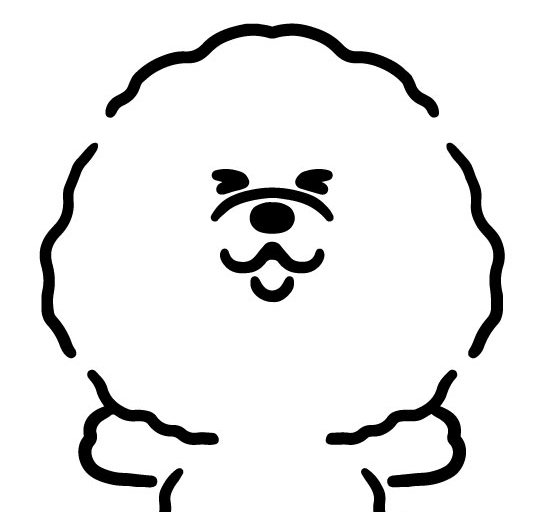
りんごの少女も、楽譜を書いた人も、実在した人物なんだって
実話『関心領域』のりんごの少女のシーンの意味をネタバレ有りで解説・考察


考察①りんごの少女は実在する?


りんごの少女の実在モデルは、
アレクサンドリア・ビストロン=コウォジェチク ストヴァルジさんです。
ポーランド人です。
アレクサンドリアさんは、グレイザー監督が、取材を進めている途中に、出会った女性です。
当時90歳でした。
しかし監督と出会った数週間後の2016年に亡くなられています。
- アレクサンドリアさんとは?
-
- 1927年7月、アウシュビッツ第2ビルケナウ収容所跡地から6マイル足らずの町、ブジェシュチェで生まれる。
(1942年4月、町はドイツ軍に支配されていた) - アレクサンドリアは12歳のとき、レジスタンス運動に参加していた。
(レジタンス運動…当時ナチス・ドイツ支配下にあったポーランドで起こった抵抗運動)
レジスタンス運動は一族に受け継がれていた。 - アレクサンドリアの父親は地元の鉱山の測量士だった。
父親は鉱山で働いていたが、鉱山をドイツ軍に鉱山を略奪されると、ポーランド人の役員と共に捕らえられた。
秘密警察に2週間拘留された後、ダッハウ強制収容所に移送され、その後釈放となった。
しかしその体重は89㎏から32kgに減っていた。
アレクサンドリアは父親の変わり果てた姿を見て、初めて気を失った。 - 90歳のときに、映画『関心領域』制作の為にアウシュヴィッツを訪れたグレイザー監督と出会い、取材に協力する。
アレクサンドリアは当時を振り返って、「わたしたちには子供時代はなかった」「すでに大人としてスタートしていた」とコメントしている。 - グレイザー監督と出会った数週間後の2016年に他界している。
- 1927年7月、アウシュビッツ第2ビルケナウ収容所跡地から6マイル足らずの町、ブジェシュチェで生まれる。
考察②りんごの少女は何をしていた?
りんごの少女が何をしていたか、結論からいうと、
りんごの少女は、囚人を飢えから救う為に、アウシュヴィッツ強制収容所に忍び込んで、りんごを忍ばせていた。(※もっと詳細に説明すると、りんごの少女は、アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所内にある彼ら囚人の勤務地に夜な夜な忍び込んでは、彼らが翌日見つけることができるような場所にりんごを忍ばせていた)
↓
りんごの少女は途中、囚人ヨセフ・ウルフが作詞作曲した『陽の光』の楽譜が入った空き缶を見つけます。
するとそれを持ち帰り、翌朝になると、ピアノで奏でていました。(美しいシーンでしたね)


りんごの少女は、盛り上がった土の斜面に、りんごを、すぽっ、すぽっ、と次から次へとはめこんでいましたね。
当人の心境を思えば、こんな悠長なことをいってはいられないですが、かわいらしいシーンでした。
りんごの少女は、小舟の中や、作業道具の物陰にも、りんごを忍ばせていきます。
そして、キャンディ缶とおぼしき物を見つけます。
中身を確認すると、それを持ち帰ります。(中身には、囚人囚人ヨセフ・ウルフが作詞作曲した『陽の光』の楽譜が押し込められていました)
りんごの少女は自転車に乗って、看守とおぼしき人影の目を盗んで、帰宅しました。
家には、娘の帰りを心配して待っていた様子の母親がいて、彼女を出迎えます。
翌朝になると、りんごの少女は、
昨日見つけたしわくちゃな楽譜を広げて、ピアノで弾いていました。
一音を一音に思いを馳せるように。
作詞作曲者は、いつももらうりんごのお礼のつもりで曲を書いたのでしょうか。
誰でも良いので、自分の魂の叫び声を聞いてもらって、抑圧された感情を発散させたかったのかもしれせんね。
後日には、りんごの奪い合いで銃殺も…
りんごのシーンには、後日談がありました。
囚人たちが、りんごの奪い合いになって、看守に銃殺されてしまうというものです。
命を救うはずのりんごが、逆に命を奪うことになるとは、皮肉なものです。
ですが救いがあるならば、ガス室送りにされて、数分~20分と苦しむことに比べたらマシだっただろうことではないでしょうか。



そのおっかにゃいやりとりを次男が窓辺で聞いていたのがまたポイントにゃ
因みに、本当に飢えてしまうと、食べたくても胃が受け付けてくれない状態になってしまいます。
お腹が空いているのに関わらず、何も食べれなくなってしまうのです。
こうなってしまうともう、差し入れをもらっても、陰で処分するしかなかったそうです。
なぜ娘がそんな危険な役割を?
なぜ子供が強制収容所という危険な場所に身を挺して忍び込まなければいけないのか?
いささか、疑問には思いませんでしたか?
母親が家にいましたが、なぜ母親が行かないのか?
なぜ母親は娘にそんな危険な真似をさせるのか?
見つかれば、強制収容所に送られるリスクがあります。
しかしナチスの看守は、ポーランド人の少女が収容所に入り込むことについては、さほど気に留めなかったのだそうです。
ということで、母親ではなく、ナチスに怪しまれない幼い娘が収容所に出入りしていた、というわけですね。
しかし命賭けであることに変わりはなく、母親も苦渋の選択だったのでしょう。



なっとく…
考察③謎の楽譜の作詞作曲者も実在する?
謎の楽譜の作詞作曲者ヨセフ・ウルフも実在する
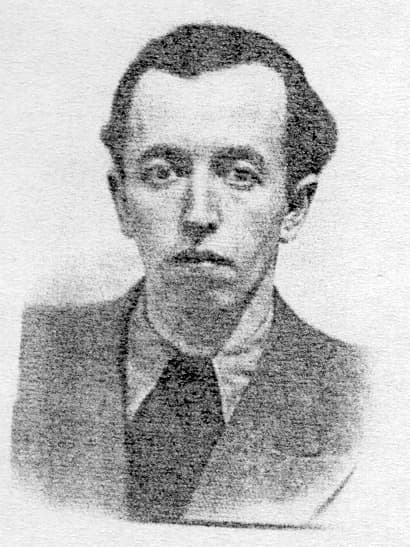
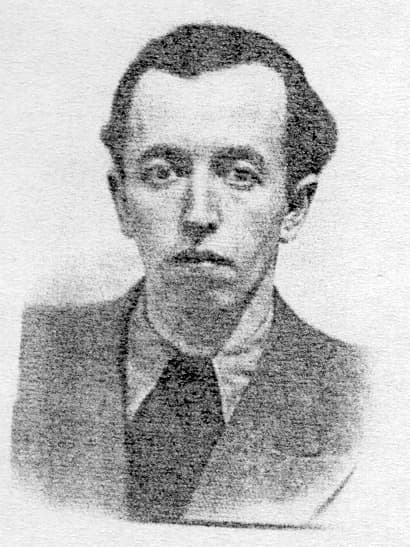
ヨセフ・ウルフ(Joseph Wulf)さんは、ドイツ系ポーランド人のユダヤ人歴史家として知られています。
ヨセフ・ウルフを記念したヨセフ・ウルフ図書館がベルリンのヴァンゼー会議博物館にあるなど、著名な方です。
第三帝国に関する本を18冊出版しました。
主な出版物としては、
・『第三帝国とユダヤ人』 (1955年)(レオン・ポリアコフとの共著)
・『ハインリヒ・ヒムラー』(1960年)
・『マルティン・ボルマン:ヒトラーの影』(1962年)
など。
ヨセフ・ウルフさんは、
1943年、ポーランドのレジスタンス運動に参加していたところ、捕らえられ、アウシュビッツ強制収容所に投獄されてしまいました。
捕まれば命はないというのは覚悟していたのでしょうが、最悪の事態に陥ってしまいました。
ポーランドのレジスタンス運動に参加していたというのは、アレクサンドリアさんとの共通点です。
つまり彼らは同士で、もしかしたら顔見知り程度の関係性はあったのかもしれません。
そして同年の1943年の内に、アウシュヴィッツ第3収容所で、『Zunenshtraln(陽の光)』の作詞作曲をしたといわれます。
詩の内容は、「からだは閉じ込められている、だが魂は燃え盛っている、自由がもうすぐそこまて来ているからた」といった、自身を鼓舞するようなものでしたね。
そして1945年1月18日、ヨセフ・ウルフさんは、あの悪名高き"死の行進"にも参加させられてしまいます。
そして1945年1月27日、"死の行進"に参加されられた内の僅かな生き残りが、ソ連軍によって、解放されました。
ヨセフ・ウルフさんも、その内のひとりで、つまり彼は"死の行進"をも生き延びてみせました。
アレクサンドリアさんのりんごが、ヨセフ・ウルフさんの命を繋いだかも分かりません。
ヨセフ・ウルフさんの妻子(ジェンタ・ファリク・ダクナーとデイビッド)も、ポーランドの農民の元に身を隠しており、戦争を生き延びたということです。
ですがしかしヨセフ・ウルフさんのご両親、兄弟、義母、姪は亡くなってしまったということです。
辛いですね。
アレクサンドリアさんとヨセフ・ウルフさんのふたりに、その後交流があったかは分かりません。
ですが、アレクサンドリアさんは、ヨセフ・ウルフさんが解放されたことはきっと知っていたでしょうから、人知れず喜んでいたのかもしれません。
しかし1974年10月10日、ヨセフ・ウルフさんはベルリン=シャルロッテンブルクのギーゼブレヒト通り12番地にある自宅アパートの5階の窓から飛び降り、自殺しました。
以下は、ヨセフ・ウルフさんが息子に宛てた最後の手紙です。
“I have published 18 books about the Third Reich and they have had no effect. You can document everything to death for the Germans. There is a democratic regime in Bonn. Yet the mass murderers walk around free, live in their little houses, and grow flowers.”
https://www.wikiwand.com/en/articles/Joseph_Wulf
和訳:第三帝国に関する本を18冊出版しましたが、何の効果もありませんでした。ドイツ人のために、どんなことでも記録に残しても無駄です。ボンには民主主義体制があります。しかし、大量殺人者たちは自由に歩き回り、小さな家に住み、花を育てているのです。
ヨセフ・ウルフさんは、3年間、東ヨーロッパのユダヤ人に関する500ページの歴史書を執筆することを計画していたといいます。
これを受け入れるという手紙が出版社から届いたのは、ヨセフ・ウルフさんが亡くなった日で、未開封のままだったといいます。
手紙が届くのがあと1日早ければ、ヨセフ・ウルフさんは自ら命を絶たずに済んだのかもしれません。
ヨセフ・ウルフさんの亡くなり方は無念なものでしたが、彼の残した功績は偉大です。
映画制作秘話:ヨセフ・ウルフの肉声だった
映画で流され『Zunenshtraln(陽の光)』は、ヨセフ・ウルフさんの実際の録音音声だということです。
アメリカ合衆国ホロコースト記念博物館によって提供されたもので、公式サイトで聴くこともできます。
映画『関心領域』は、とことん真に迫っていますね。
考察④ヘンゼルとグレーテルの意味は?


ヘンゼルとグレーテルが朗読されている理由。
これは、実話に基づいているようです。
2013年、ワシントンポストにルドルフ・ヘスの三女のインタビュー記事が公開されてました。
その中に、
"父親はやさしい人で、一緒にヘンゼルとグレーテルの物語を読んだ"
と記述があります。
その他にも、
『ヘンゼルとグレーテル』と『関心領域』を対比させることで、
ルドルフ・ヘスが自滅の道へと突き進んでいることを示唆していたのかもしれません。
その場合、次のように置き換えられます
ヘンゼルとグレーテル=りんごの少女
パン=りんご
魔女=ナチス(ルドルフ・ヘス)
子供をいじめる悪役は結局、最後にはやられてしまいます。
魔女はヘンゼルとグレーテルにやっつけられてしまいますし、
ルドルフ・へスは、1947年4月、戦犯としてアウシュヴィッツで絞首刑に処されることになります。
そう考えると、ルドルフ・ヘスが『ヘンゼルとグレーテル』を朗読していたというのは、皮肉な話ですよね。
りんごの少女が出てくるシーンは、不穏な雰囲気で、今に少女の身に何か起こるのではないかと、観ていてヒヤヒヤした人も多かったのではないかと思います。
しかし本当に案ずるべきであったのは、りんごの少女の方ではなく、ルドルフ・ヘスの方だったということなのかもしれません。
子供たちは、父親がまさか童話の中に出てくる魔女だったとは、思いもしなかったでしょう。
ルドルフ・ヘス自身も、そのような自覚はなかったのだと思います。
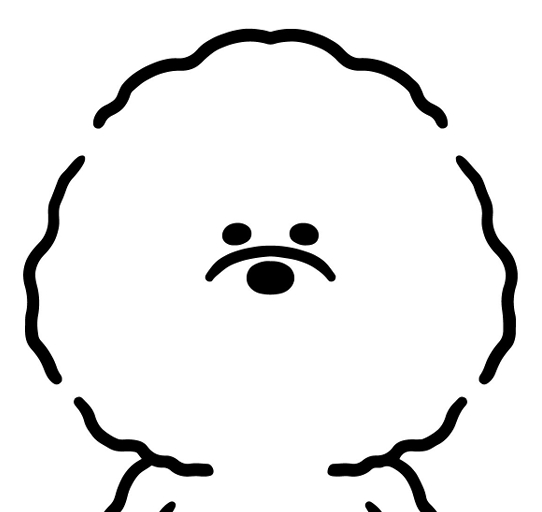
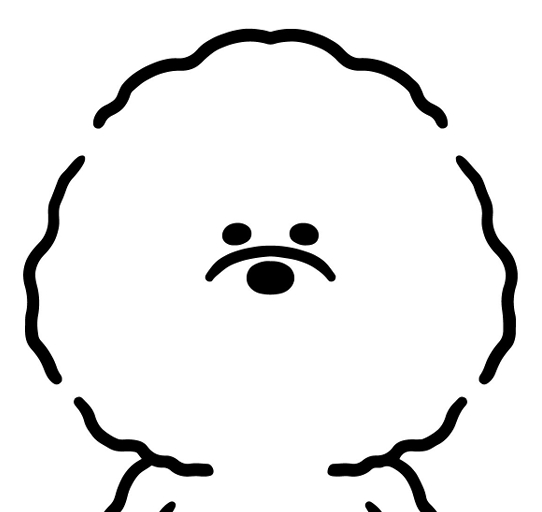
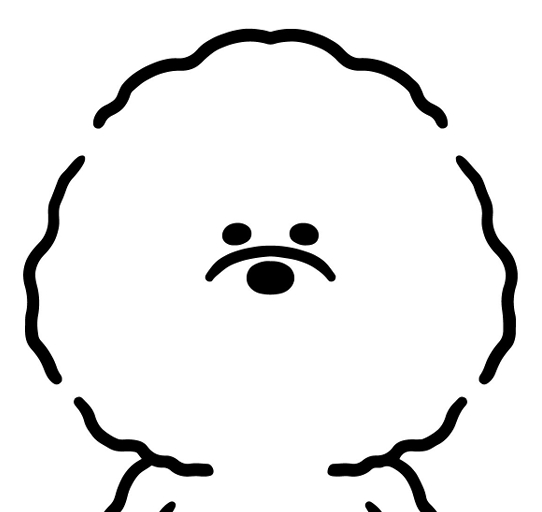
おうちでは子ども思いのパパなのにね
ルドルフ・ヘスは何を考えていたのか?は、次の記事を参考にして下さい
ホロコーストはリアル版『ヘンセルとグレーテル』だった
ホロコーストでは、
「ユダヤ人」というだけで約600万人の人が犠牲になったと見られています。
が、その内の150万人が、15歳以下の子供でした。(NPO法人ホロコースト教育センターより)
ヒトラーは、子供相手にも容赦がありませんでした。
むしろ、ユダヤ人の子は悪印因子であり、処分することが重要だと考えていました。
子供は労働力にもならない為、絶滅収容所に送られたり、非道な人体実験に回されたりました。(有力者の子供はうまく匿われることも)
まるで、リアル版ヘンゼルとグレーテルです。
いや、それよりもひどい、
作り話より作り話のような実話でした。
考察⑤りんごの少女のシーンをサーモグラフィカメラで撮影した意味は?
『関心領域』でりんごの少女のシーンをサーモグラフィカメラで撮影した意味は、
作り手の存在を感じさせない為。
✔️これは、グレイザー監督が、メディア(TheGuardian)のインタビューに対し、"映画を作者のいないものにすることが目的だ"と回答していた為です。
グレイザー監督は、"映画を作者のいないものにする"為、他にも次のような工夫を施していました。
・日中の撮影も、太陽光(自然光)のみで撮影することにこだわる。
・ヘス家や庭などに複数の隠し固定カメラを仕込む。(俳優たちは、撮影スタッフがいない状況で撮影に臨む)
これらのお陰で、観客側は、まるで本当に彼らの私生活を覗いているかのような気にさせられました。
りんごの少女のシーンにも、まるでドキュメンタリーを観ているかのような、スリルさがありました。
りんごの少女のシーンで、仮にもし本当はそこに存在するはずのない照明の光が当たっていたら?
きっと、ここまでの臨場感は得られなかったはずです。
りんごの少女も実際には、照明ひとつない暗闇の中を、手探りで手探りで進んで、りんごを仕込んでいっていたことでしょう。
人間の温かみを表現する
他にも、サーモグラフィカメラを使用することによって、人間の体温を視覚的に表現することができます。
人間の体温=人間の温かさ
に置き換えることができます。
グレイザー監督は、りんごの少女(アレクサンドリア)を、"映画の中の唯一の光"だと話しています。
考察⑥りんごの少女のシーンは一体何を伝えたかったのか
結論、
監督は、りんごの少女を通して、"Force for Good"(人々がより豊かになる為の力)を伝えたかったのではないかと思います。
グレイザー監督は、りんごの少女(アレクサンドリアさん)のことを、"Force for Good"だと話していました。
グレイザー監督は、りんごの少女の行動が、人々をより豊かにする為の力になると感じたようです。
以下、グレイザー監督のインタビュー記事です。▼
He pauses for a long moment. “That small act of resistance, the simple, almost holy act of leaving food, is crucial because it is the one point of light. I really thought I couldn’t make the film at that point. I kept ringing my producer, Jim, and saying: ‘I’m getting out. I can’t do this. It’s just too dark.’ It felt impossible to just show the utter darkness, so I was looking for the light somewhere and I found it in her. She is the force for good.”
https://www.theguardian.com/film/2023/dec/10/jonathan-glazer-the-zone-of-interest-auschwitz-under-the-skin-interview
和訳:その小さな抵抗の行為、食べ物を残すという単純で、ほとんど神聖な行為は、ひとつの光明となるため、非常に重要だ。あの時、私は本当にこの映画は作れないと思った。プロデューサーのジムに何度も電話して言ったんだ。「もう無理だ。暗すぎる」と。ただ真っ暗闇を見せるのは不可能だと感じたので、どこかに光を探していて、彼女の中にそれを見つけたんだ。彼女は善の力なんだ。
彼女の行動が、スランプ状態に陥っていたグレイザー監督を救う一筋の光となったように。
"Force for Good"
世界がどれほど残酷でも、
何もできない自分の為に、
命を張ってでも食べ物をくれようとする人はきっといる。
願わくば、自分がそういう人間でありたいですよね。
その思いは確かに世の中を明るいものにしていく力になるのでしょう。
アレクサンドリアさんは、
きっとそのような温かい力を届けてくれているのでしょう。
映画制作秘話:りんごの少女がいなければ『関心領域』は完成しなかった
りんごの少女のシーンは、スリルながらも心温まるシーンでした。
りんごの少女だけが唯一、壁の向こうに関心を持って行動していたのです。
グレイザー監督は、アレクサンドリアさんのことを、暗すぎる暗闇の中の"唯一の光"だと話していましたね。
グレイザー監督は、アレクサンドリアさんとの出会いがあったので映画を完成させることができたと振り返っています。
それまでは、ただ暗いだけのこの映画を作ることはもうできないと、途方に暮れていたのです。
しかしアレクサンドリアさんとの出会いによってグレイザー監督は好機を得て、ついには映画を完成させることができたのです。
『関心領域』は数多くの名誉ある賞を受賞しました。
アカデミー録音賞(2024)
カンヌ国際映画祭 グランプリ(2023)
英国アカデミー賞 英国作品賞(2024)
全米映画批評家協会賞 主演女優賞(2024)
アカデミー国際長編映画賞(2024)
英国アカデミー賞 外国語作品賞(2024)
英国アカデミー賞 音響賞(2024)
全米映画批評家協会賞 監督賞(2024)
サテライト賞 外国語映画賞(2024)など
12歳の少女は、夢にも思わなかったでしょう。
まさか自分の取った行動が、未来の映画監督までをも救うことになるとは。
ましてや、自分の名が世界に知れ渡る日が来ようとは。
感慨深いですね。
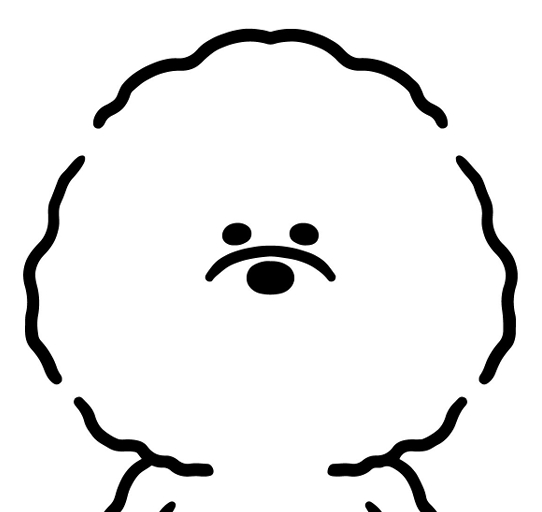
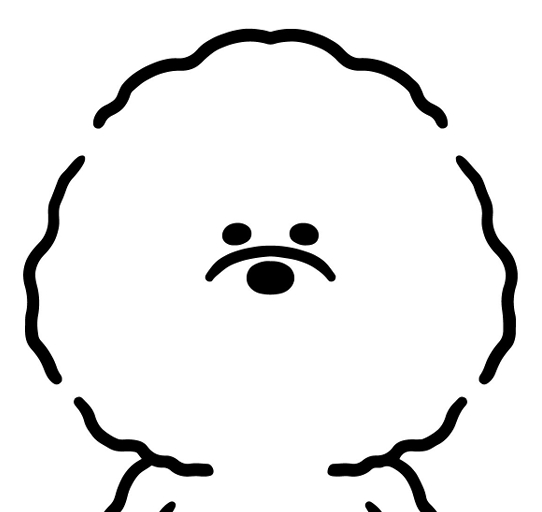
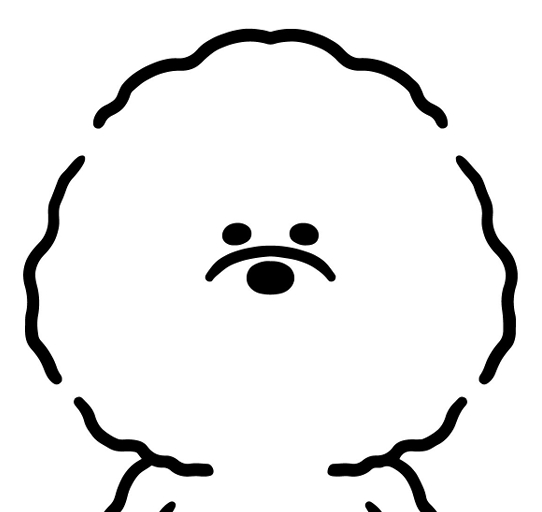
名も無き少女が英雄となって、この先も後世に力を与え続けるなんて、すごい
しかしアレクサンドリアさんは、映画公開日までに亡くなられてしまいます。
グレイザー監督はアレクサンドリアさんの訃報を受け、大変ショックを受けたそうです。
グレイザー監督にとっても、アレクサンドリアさんは、『関心領域』を最も観てもらいたい内のひとりだったのではないでしょうか。
アレクサンドリアさんがもし、現地ポーランドの映画公開日(2023年2月9日。※Google調べ)までご存命であったとしたなら、彼女は95歳だったということになります。
そう考えると、アレクサンドリアさんに『関心領域』を観賞してもらうことも、決して叶わぬ夢ではなかったと感じますよね。
それと同時に、ナチスがまだそう遠い昔の話でないことにも、気が付きます。
しかし、『関心領域』を撮るのは本当に大変なことだったんですね。
観る方は、それがたとえどんなに耐えがたい内容でも、2時間もすれば終わってしまうので気が楽ですが、作り手ともなるとそうもいきませんね。
血肉を注いで作った作品が、観る人に暗い気持ちしか与えないなんてことになったら、確かに想像するだけでも耐えられませんよね。
グレイザー監督は、取材を進めていく過程で、なんて暗いのだろうと、ほとほと嫌気が差していたのでしょう。
そこでアレクサンドリアさんに出会ってしまったら、彼女の取った行動を、何がなんでも描かずにはいられなかったでしょうね。
りんごの少女のシーンはどこまで実話なのか?
『関心領域』は、実話に基づいて制作されています。
りんごの少女のシーンも、事実に基づいて構成されていると考えて良いです。
▼参考文献
The scene came about as a result of Glazer meeting a 90-year-old woman called Alexandria, who had worked for the Polish resistance when she was just 12. She recounted how she had cycled to the camp to leave apples, and how she had found the mysterious piece of written music, which, it turned out, had been composed by an Auschwitz prisoner called Joseph Wulf, who survived the war.
引用元:TheGuardian(https://www.theguardian.com/film/2023/dec/10/jonathan-glazer-the-zone-of-interest-auschwitz-under-the-skin-interview)
和訳:このシーンは、グレイザーさんが、12歳のときにポーランドのレジスタンス活動のために働いていたアレクサンドリアという90歳の女性と出会った結果として生まれた。彼女は、リンゴを残すためにキャンプまで自転車で行った経緯と、どのようにしてリンゴを残したかを語った。謎の音楽が発見されたが、それは戦争を生き延びたジョセフ・ウルフというアウシュヴィッツの囚人によって作曲されたものであることが判明した。
アレクサンドリアさんが残した当時の日記には、
「日中に食料や医薬品を収容所に持ち込むことはできなかったので、私たちは夜に出かけた」
と綴られています。
この記述から、りんごだけでなく、医薬品も届けていたことが分かります。
この日記は、ポーランドの協会『アウシュビッツ・メメント保存協会』によって大切に保存されているということです。
映画制作秘話:家も自転車もドレスも本物
『関心領域』のりんごの少女のシーンの撮影に使われた家やピアノ、自転車やドレス(屋根裏部屋から出てきたらしい)は、なんと全てアレクサンドリア本人のもの。
取材に完全協力してくれたのです。
因みに、撮影でメインに使われたヘスの家。
あれについても、制作側がアウシュヴィッツ博物館の理事の許可を得て、収容所の敷地のすぐ外にある空き家を借り受け、記録写真と生存者の証言を元に、ヘス一家が約4年間暮らした別荘を丹念に再現したということです。
作品にかけられた並々ならぬ熱意が感じられますよね。
『関心領域』は完成までに、10年もの月日を要したといいます。が、それはそうなるわけだと思うわけです。
これらの事実を踏まえた上で、もう一度『関心領域』を見返してみたくなりました。
あとがき
以上となりましたが、お読みになって下さった感想は、どんなものでしたか。(最後までお読み下さり、どうもありがとうございます)
りんごの少女が、まさか実在していたとは、驚きましたね。
りんごの少女の行いは、きれいで、まるで作り話のようにも感じられましたから。
しかも、グレイザー監督とも会っていたとは。
ふたりの出会いに感謝ですね。
しかし、アレクサンドリアさんが映画公開前に亡くなられていたことは、ショックでした。
それも監督に出会って数週間後とは、まるでもうやり残したことはないといわんばかりのタイミングでしたよね。
やはり完成した映画を観てもらいたかったですね。
アレクサンドリアさんは、少女だった頃の自分の行いを観て、何を思ったのでしょうか。
多くの英雄と同じように、当然のことをしたまでだと思ったのでしょうか。
一言でも良いので、感想を聞いてみたかったですね。
ひどい時代で、決して気楽な思い出ではないと思いますが。
当時いくらナチスのポーランド人の少女に対する監視が緩かったといっても、
その固くなるきっかけは今になるかもしれませんでした。
『関心領域』は、実話に基づく映画です。
そのこと自体は容易に想像がつくかと思いますが、想像以上に実話ベースでした。
りんごの少女の自転車、ドレス、ピアノや住んでいる家まで、実際に使われたのものだったというのですから。
そして『陽の光』を作詞作曲をしたヨセフ・ウルフさんの実際の音声まで流されていたというのですから、驚きです。
再現性が著しいですよね。
ということで、りんごの少女のモデルは、当時12歳でポーランドのレジスタンス運動に参加していたアレクサンドリアさんでした。りんごの少女のシーンも、実話です。
参考文献:
TheGuardian
ホロコースト百科事典
wikiwand
WEEKENDCINEMA
Hollywoodreporter
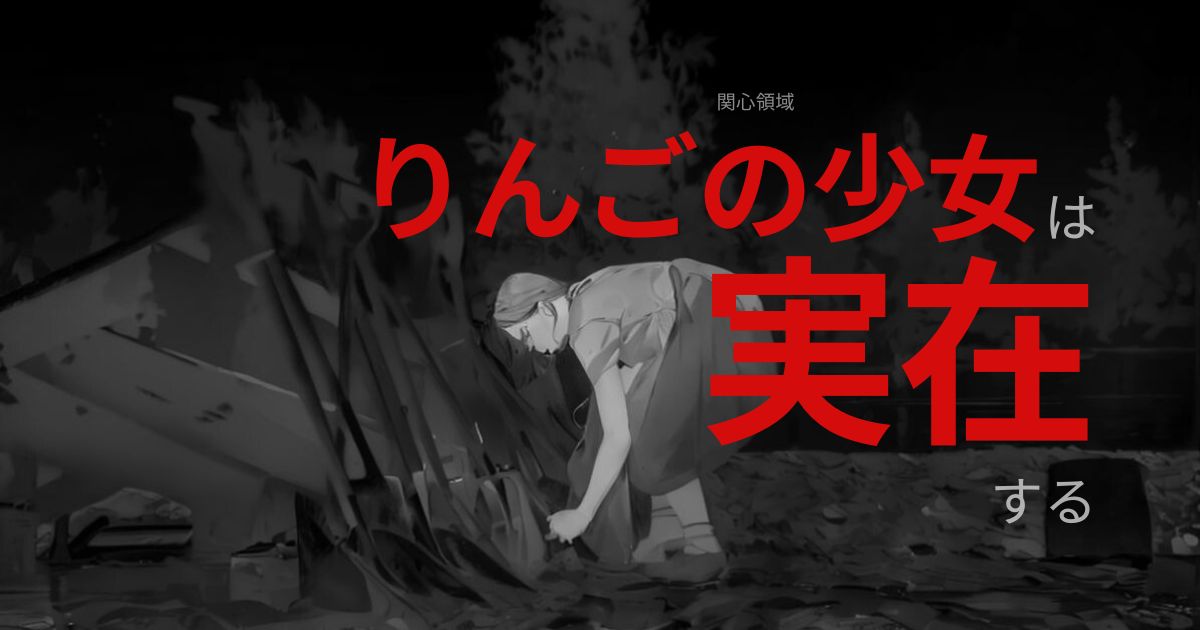
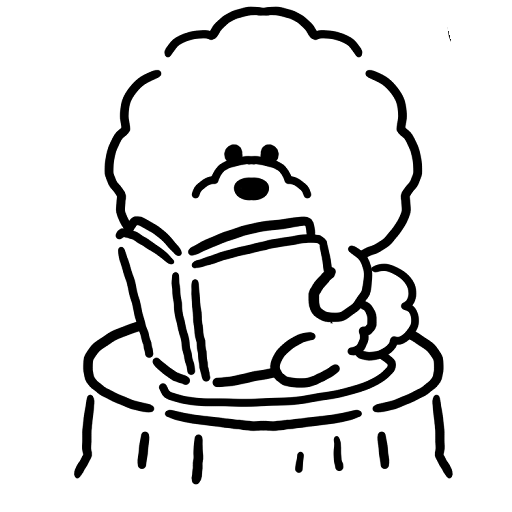
コメント